その声の方向を見ると、そこには、銃を構えた数人の覆面姿の男が立っていた。
「ええと……これは……」
よく状況が呑み込めない。全員が、動きを止めていた。
すると覆面達は、銃を向けてさらに叫んで来た。
「大人しく、酢乙女あいを渡してもらおうか!!」
(これって……)
相手は、銃を持っている。酢乙女あいを連れて行こうとしている。
それが意味するのは………誘拐?
(えええええええ!!??)
いくらなんでも、えええええ!?
あいちゃんは老人の陰に隠れて震えている。
超大企業の御令嬢だからだろうか。誘拐して身代金って流れだろう。
不思議と、頭は冷静だった。
あまりに現実味が無さ過ぎて、第三者的立場にいる感覚なのかもしれない。
「――チョット待チナ!!」
「―――ッ!!」
突如、逞しい方々が覆面達の前に立ちはだかった。
「オ嬢様ニハ……手ヲ出サセナイゼ!!」
そして男達は、一斉に覆面達に向かって行った。
ここぞとばかりに、自らの武勇を示すかの如く、逞しい方々は飛び掛かる。
勇ましい。実に勇ましい。
覆面達は銃を使う暇もなかったようだ。肉体と肉体による、激しい乱闘が始まる。
まるで映画のワンシーンのようだ。
オラは見物客だけど。しかし、アピールするには確かに最適かもしれない。
何も出来ないにしても、オラも何かすべきだろうか―――
――その時、オラの目が捕えたのは、恐怖のあまり涙するあいちゃんの姿だった。
その姿を見たオラは、無意識にあいちゃんの方に走り出していた。
そして震える彼女の体を掴み、声をかけた。
「あいちゃん!!大丈夫!?」
「し、しんのすけさん……」
とりあえずは大丈夫のようだ。とにかく、彼女をどこかへ避難させないと……
「あいちゃん!!まずここを逃げ―――!!」
「――試験!!終了~!!」
突然、試験官のおじいさんが声を張る。その声に、全員が動きを止めた。
「………へ?」
全員が動きを止める中、さっきまで泣いていたあいちゃんがすくりと立ち上がった。
「ええと……あい、ちゃん?」
「……しんのすけさん、騙してごめんなさい」
「……どういうこと?」
すると、あいちゃんはクスリと笑った。
「――これが、試験なんですよ。私の身が危なくなった時、真っ先に私に駆け寄って来るかどうかを確かめるための……」
「え?え?で、でも、あいちゃん震えてたし……それに、泣いてたし……」
オラの言葉に、あいちゃんは更に微笑む。
「……私の演技も、なかなかでしょ?」
(あ、あいちゃん……そりゃないよ……)
あいちゃんの説明に、筋肉隆々の男達はぶーぶー文句を言い始める。
「ナンダヨソレ!!」
「聞イテナイヨ!!」
……とまあ、好き勝手叫びまわっていた。
だがここで、試験官の爺さんが口を開く。
「――お黙りなさい!!」
それまでの彼とは全く違う、覇気のある言葉だった。
試験官の言葉に、男達は固まる。
「……お嬢様の身が危ないというのに、自分の評価のために、お嬢様を差し置いて犯人に飛びかかるとは何事ですか!!
あなた方は、これが何の試験か分かってるのですか!?
あなた方の行動は言語道断!!プロとしての意識が欠如し過ぎている!!――失格で、然るべきです!!」
「……」
男達は、黙り込んだ。
暑苦しい男達は、今にも泣きそうな顔をしていた。
鬼の目にも涙、か……
「……今回の試験の結果は、言うまでもありません。――合格者は、しんのすけさんです!!」
「……オラが?」
「しんのすけさん!!やりましたね!!さすが、私が見込んだだけありますわ!!」
「……う、うん!よくわからないけど、やったよあいちゃん!」
あいちゃんは本当に嬉しそうにしていた。それを見ていたら、オラもようやく試験を合格した実感がわいてきた。
もうダメかと思ったけど、諦めないで良かった!!
本当に!!
そして試験官は、締めの言葉を告げる。
「――これにて、“あいお嬢様ボディーガード選抜試験”を、終了します!!」
………何か、言った。
「…………え?今なんて?」
すると、あいちゃんはさも当然のように言う。
「ですから、私のボディーガードを募集する試験ですよ。
――しんのすけさん、今日からあなたは、私のボディーガードですわ」
あいちゃんは、嬉しそうに微笑みかけてきた。
……でも、それどころじゃない……
「聞いてないよおおおおおおおおおおお……!!!」
オラの叫びは、建物の壁に反響し、大きく響き渡っていた……
「……お兄ちゃん、どうしたの?」
「……いや、別に……」
疲れ果てて、オラは家でぐったりしていた。
ボディーガードという名目でなってはいるが、ほとんど秘書のような存在だった。
あいちゃんのスケジュールを調整し、送迎をする。何か希望があれば、可能な限りそれに応える。
これまで、黒磯さんが一人でしていたことだ。
黒磯さんは感激していた。
何でも、ようやくあいちゃんも認める後継者が出来たとか。
黒磯さんに、仕事のいろはを叩きこまれる毎日だった。
(あの人、これをあいちゃんが小さい頃からやってたんだよな……タフなはずだ……)
いずれにしても、給料面はかなり上がった。以前勤めていた会社よりも、ずっと。
だがその分体力を消費するのは否めない。工場よりも、ずっと。
……その時、ひまわりが小さく呟いてきた。
「――お兄ちゃんさ……なんか、私に隠してない?」
「……え?」
ひまわりの方を振り向いた。彼女は、とても辛そうな顔をしていた。
「……隠すって……」
「……私さ、今日、お兄ちゃんの会社に行ったんだよね。久々に、一緒に帰ろうって思って……」
「―――ッ!」
「上司の人に聞いたよ。――お兄ちゃんが、会社を辞めたこと……」
「そ、それは……」
ついに……気付かれてしまった。いずれ言おうと思っていたことだった。だが結果として、秘密にしていたとも言えるだろう。
ひまわりは、とても悲しそうに目を伏せていた。
「……だから言ったじゃん。お兄ちゃん、すぐなんでも背負っちゃうって……。何で私に何も言ってくれないの?
――そんなに、私が信じられない?」
「い、いや……そうじゃなくて……」
「――だったら何!?黙ってれば私のためになると思った!?お兄ちゃんはいつもそう!私に気を使って!!私に黙って!!」
「……」
「……いつも勝手に決めて、何も話してくれない……お兄ちゃんは、私の気持ち考えたことあるの!?」
……ひまわりの叫び声に、室内は静まり返った。
オラは、何も言えなかった。反論すら、出来なかった。
「……もういいよ……!!」
そう言い捨てると、ひまわりは2階の自分の部屋に駆けあがって行った。
オラは、その姿を見ることしか出来なかった。
「……ひまわり……」
「――しんのすけくん、どうかしましたか?」
車を運転してい黒磯さんは、ふいに話しかけて来た。
「え?」
「顔が、落ち込んでいますよ?」
「は、はあ……」
この人は、たぶん人をよく見てるんだと思う。長年この仕事をして培われた、洞察力みたいな。
この人の前だと、隠し事なんて出来ないな――
そう、思った。
「……ちょっと、妹とケンカしまして……」
「妹……ひまわりさんのことですか?」
「はい。隠し事が、ばれちゃったんですよ。心配かけないように黙ってたんですが、逆に心配かけちゃったみたいで……」
「……仕事の、ことですか?」
「……はい」
「………」
黒磯さんは、何かを考えていた。そして、急にハンドルを切る。
それは、本来向かうべき方向とは、違う方向だった。
「……少し、休憩しましょう。この先に、海が見える見晴らしのいい波止場があります。コーヒーくらい、奢りますよ」
「はあ……」
波止場に着いたオラと黒磯さんは車を停め、海を眺める。
手にはコーヒー。
黒磯さんは、タバコを吸い始めた。
「……お嬢様には黙っててくださいね。タバコ、嫌いなんですよ」
「……分かりました」
オラと黒磯さんは、海を眺める。
遠くに見える雲はとても大きく、海鳥の声が耳に響き渡る。潮の香りは、どこか心地いい。
海を眺めながら、黒磯さんは話してきた。
「……私も、妻とケンカしたら、よくここに来るんですよ」
「……上尾先生――ああ、今は、黒磯先生でしたね。奥さんとですか?」
「はい。彼女、メガネを外すと気性が荒いでしょ?だから、しょっちゅう……」
黒磯さんは、照れ臭そうに話す。
黒磯さんと上尾先生は、結婚していた。もう、十数年前の話だ。
確かに、上尾先生はメガネを外すと強気になる。それでも、黒磯さんとは幸せに生活してるようだ。今の黒磯さんの表情が、それを物語る。
「……一緒に暮らしていれば、ケンカの一つや二つくらい、いつでもあります。相手に分かって欲しい。自分の気持ちを、言葉を、相手に伝えたい。
そんな想いが、ぶつかり合うのがケンカですから」
「………」
「ひまわりさんだって、そうじゃありませんか?もちろん、しんのすけくんも。そういう時は、とことん話し合うべきです。
ケンカはしないに越したことはありません。……ですが、たまのケンカは、時にいい方向に転ぶこともあります。
――雨降って地固まる、ですよ」
「………」
すると黒磯さんは、タバコの煙を吐いた後、コーヒーを一口飲んだ。
「……今日は、家に帰ってあげてください。お嬢様には、私から説明しておきます」
「え?でも……」
「ひまわりさんに、よろしく言っておいてください」
黒磯さんは、そう言って笑っていた。サングラスの奥には、優しい眼差しが見えた。
オラは頭を下げて、その日は、家に帰った。
オラは家に帰って、食事の準備をした。
このところ忙しくて、手抜き料理ばかりを作っていた。
だから今日は、ここぞとばかりにひまわりの大好物を用意する。
今日は、とことんひまわりと話す……そう、決めていた。
考えてみれば、オラは、いつまでもひまわりを子供扱いし過ぎていた気がする。
彼女も、もう大人なんだ。
きちんと向き合って、とことん話してみようと思う。
食卓を、二人で囲んで。
「―――遅いな……」
……だが、ひまわりはなかなか帰ってこなかった。チラチラと時計を見るが、いっこうに戻らない。
電話にかけても通じない。彼女から、返信があることもなかった。
(いったい何してるんだよ……もしかして、事故か何かに……)
なんの音沙汰もない時間が、不安を駆り立てる。
しかし、どれだけ待っても、彼女が帰ることはなかった。
――そして、ひまわりが帰らないまま、朝を迎えた。
「……もう朝か……」
朝日が射し込む窓を見て、オラはふと呟く。
本当に、何があったのだろうか……
嫌な記憶が、脳裏に過る。
あの時、真夜中に電話が鳴り響き、変わり果てた父ちゃん達を迎えに行った。
しかし何か起こってるなら、電話があっててもいいはず……
「……帰ったら、こりゃ説教だな」
そう……きっと帰ってくる。
そしてひまわりは言うんだ。
「友達の家にいた」って……
――その時、家の電話が鳴り響いた。
「――ッ!」
一気に、心拍数が上昇したのが分かった。
ヨロヨロと立ち上がり、電話機に向かう。目と鼻の先にあるはずの電話機が、とても遠く感じた。
伸ばす腕が震える。
そして、受話器を耳に当てた……
「……もしもし、野原です……」
「あ!野原さんですか!?」
「は、はい……あの……」
「野原ひまわりさんという方は、ご家族におられますか?」
「はい。僕の妹ですが……」
「ああ、良かった!――課長!ご家族の方に連絡取れました!」
電話の向こうの相手は、誰かに報告していた。とてもガヤガヤしている。
……その様子は、以前経験したことがあった。
「あ、あの……」
「ああ、失礼。私、◯◯警察署の者ですが――」
「――」
目の前が、真っ白になった。
足の力は抜け、その場に崩れるように座り込んだ。
「大丈夫ですか!?」
「――え?あ、はい……それで、ひまわりは……」
「実は、ひまわりさんが事故に遭いまして……」
「……そ、それで、無事なんでしょうか――」
「……はい。命に別状はありません」
「そ、そうですか……」
身体中の緊張が、一気に解けた気がした。
だが警察官は、言いにくそうに続けた。
「――命に別状はありませんが……ただ――」
「……え?」
「―――」
「―――」
……それ以降の会話は、よく覚えていない。
「――いやぁ!参っちゃった!」
「まったく……ケータイ忘れてた時に車に跳ねられるなんて……おかげで、警察官もお前が誰なのか分からなくて苦労したみたいだぞ?会社だって閉まってるし……」
「いやぁ、面目ない……」
「まあ、命が無事だっただけマシだよ」
「うん。そうだね」
ひまわりは、帰る途中に事故に遭ってた。
普段あまりものを持ち歩かない性分が災いし、確認に時間がかかってたとか。
とにかく、命が無事なら、今はそれでいい。
――ただ……
「……足は、どうだ?」
「……うん。感覚、ないんだ。たぶん、もう歩けないって……」
「そう、か……」
ひまわりは、歩けなくなっていた。
腰を、強く打ったらしい。
外見上では、彼女は悲観してはいないようだ。
母ちゃん譲りの明るさのおかげだろうか。
それでも、心の内は分からない。
「……あ、そろそろ検診の時間だよ」
「……分かった。後でまた来るよ」
「うん。……お兄ちゃん、ごめんね」
「なんでお前が謝るんだよ。生きてるだけで、本当に良かったよ」
「うん……」
そして、オラは病室を出る。
その直後、病室から、こもった声が聞こえてきた。
「……ひぐっ……ひぐっ……」
「………」
その声に、心は激しく痛む。
でもこれからは、オラがもっと支えないといけない。
そう決心し、ひまわりの声が漏れる病室を後にした。
ひまわりは、しばらく入院することになった。
その間、オラは家の整理をすることにした。
あいちゃんに、事情を説明ししばらく休みを取ることを告げた。
快く了承してくれたことに、本当に感謝してる。
おそらく、これから車椅子が主体となる。
ほんの少しの段差が、彼女にとって大きな障害だろう。
段差という段差に、片っ端からスロープをつける。
問題は、台所と洗面所、浴室だろう。
こればかりは、改築しないと無理だろう。
困り果てていた、その時――
「――ごめんください」
突然、誰かが訪ねてきた。
「はーい……って、あいちゃん?」
「ごきげんよう、しんのすけさん」
そこには、あいちゃんがいた。
「どうしたの、こんなところに……」
するとあいちゃんは、ニコリと笑みを浮かべた。
「しんのすけさん、実は、お話があるのですが……」
「話?」
「はい。我が酢乙女グループでは、介護用品にも力を入れています。その新商品が出来たので、テスト運用をしてもらいたいのです」
「テスト運用?」
「はい。――黒磯」パチン
あいちゃんが指を鳴らすと、家の中に、一台の車椅子が運び込まれた。
「これは……車椅子?」
「はい。ですが、ただの車椅子ではありません。
……百聞は一見にしかず。――黒磯」
「はい……」
彼女の号令に、黒磯さんが車椅子に座る。
「まず、これは内部バッテリーを付けており、軽く車輪を回すだけで、スムーズに移動することが可能なんです」
「へぇ……電動自転車みたいなものか……」
「そして、最大の特徴が……」パチン
再び彼女は指を鳴らす。
すると、黒磯さんが座っている座席が、上に延び始めた。
「これは……」
「座席は、最大1mまで延びることが可能で、床下20?まで下げることもできます。これなら、車椅子の上り下りも容易く、少々の高いところの作業も出来る、新型車椅子なのです」
「凄い……でも、なんだか悪いよ」
「それには及びません。先ほども言ったとおり、これはテスト運用です。月に一度レポートを提出してもらいます。
こちらも、貴重な資料にさせてもらいます」
「……分かった。ありがとう、あいちゃん」
「礼には及びません。……しんのすけさん、私に出来ることがあれば、何でも言ってくださいね」
そして、あいちゃんは帰っていった。
こうして、ひまわりを迎える準備は、着々と整いつつあった。
それから、ひまわりの退院の日を迎えた。
「うわぁ……!」
ひまわりは、家の変わりように声を上げる。
家の中は、すっかり変わっていた。
タンスは全て一回り低いものに変え、大概のものが車椅子のままでも手の届く位置に置いた。
まるでリフォームでもしたかのような室内は、久しく家に戻らなかった彼女にとって、新鮮なものだろう。
「これなら、だいぶん過ごしやすくなると思うから」
「……うん。ありがとう」
言葉とは裏腹に、ひまわりからは、さっきまでの元気はなくなっていた。
顔も、どこか辛そうにしている。
「……どうした?」
「……ごめんね、お兄ちゃん。私のせいで、お兄ちゃんに迷惑をかけて……」
「……」
ひまわりは、完全に俯いてしまった。
それは、彼女の心からの言葉なのだろう。
――だからこそ、オラは彼女にデコピンをする。
「ていっ」
「あいたっ!」
ひまわりは、おでこを押さえたまま、目を丸くしてオラを見ていた。
「なに妙な遠慮してんだよ。オラとお前は他人か?」
「……」
「違うだろ。家族だろ。お前の、しょうもない遠慮なんて、オラには通じないからな。
お前が歩けないなら、オラが後ろを押してやる。オラは、お兄ちゃんだからな。
――だからお前も、妙な気を使うなよ」
「……うん……うん……!」
ひまわりは、涙を堪えながらずっと頷いていた。
……そうだ。オラは、ひまわりのお兄ちゃんなんだ。
オラが、ひまわりを支えるんだ。
改めて、そう決意した。
それからの生活は、色々大変だった。
続きをご覧ください!



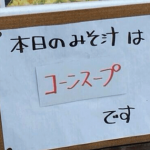











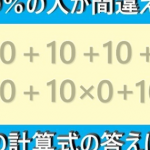









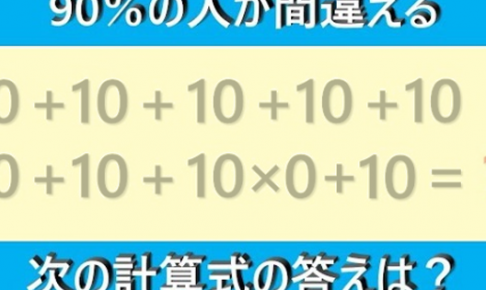

コメントを残す